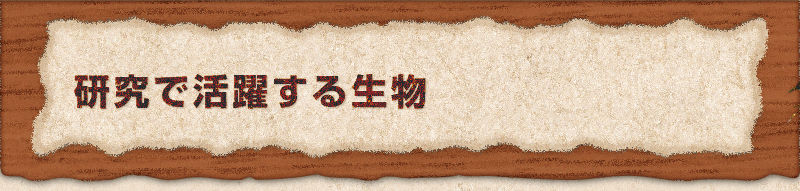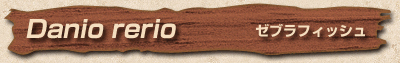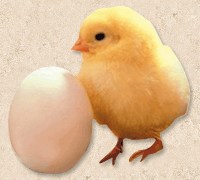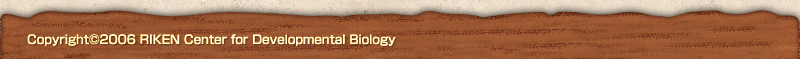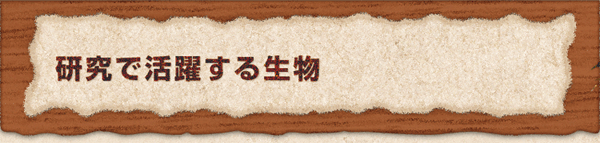
細胞、遺伝子レベルでの研究やゲノム解析が進むにしたがい、基本的な発生メカニズムは多くの生物で共通することが分かってきました。いろいろな生物を比較することで、生命の「共通原理」と「多様性の神秘」が解き明かされ、「生命」そして「ヒト」が見えてくるのです。
初期発生の研究が最も進んでいる脊椎動物
カエルの卵は約1ミリと大きく、その受精と発生は水中でおこるので、卵や胚の操作が比較的簡単です。またホルモンの投与で排卵を簡単に誘発できるので卵を沢山とることができ、「量」を必要とするタンパク質レベルでの研究にも適しています。受精から24時間以内に将来脳などの神経系をつくる神経管が形成されるといった、初期発生の速さとダイナミックさも発生生物学者を魅了しています。

プラナリアに学ぶ幹細胞と再生のメカニズム
プラナリアはその高い再生能力で知られ、数十の断片に切断しても、それぞれが完全なプラナリアにまで再生します。この再生能力を可能にしているのは全身に散在する全能性幹細胞であることが明らかになってきました。現在、再生現象に始まり、進化や代謝における幹細胞の役割といった側面からもプラナリアを用いた研究が進められています。

ノーベル賞を生み出した突然変異体の宝庫
20世紀の始めに遺伝学の研究材料として取り上げられて以来、ノーベル賞研究を含む多くの重要な発見がなされてきました。現在でも、発生の遺伝的な仕組みを理解するのに適したモデル生物として盛んに研究されています。とりわけ発生や形態に異常を示す突然変異の研究により、「体の設計図」を構成する遺伝子が多く見つかり、ヒトでも同様の遺伝子が働いていることが分かってきました。
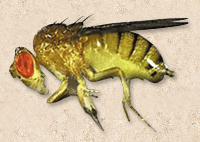
受精卵から全細胞への系譜が描けるモデル生物
959個の体細胞からなる成虫の体は、神経や筋肉といった動物の基本構造を備えています。受精卵が成虫になるまでの細胞系譜(細胞が分裂する回数や分化する方向)が明らかにされているため、多細胞生物のモデルとして非常に有用です。ゲノム(全てのDNA塩基配列)も解読され、発生における細胞運命の決定や形態形成(動物の形づくり)にどの遺伝子がどのように働いているのか解析が進められています。

遺伝子操作で探る哺乳類発生メカニズム
哺乳類であるマウスはヒトに最も近いモデル動物の一つとして重要です。遺伝子を担うDNAの塩基配列も全て解読され、ヒトとあまり変わらないことが分かりました。現在では、マウス胚の顕微操作による遺伝子導入、遺伝子ノックアウト、クローンマウスの作成といった様々な手法が発達しています。そのためマウスはヒトの遺伝子レベルの研究や疾患モデルとして非常に重要な役割を果たしています。