
第3回勉強会
天文分野のサイエンスコミュニケーション実践事例
講師:天文学普及プロジェクト「天プラ」高梨直紘氏、佐藤祐介氏(北大CoSTEP)
おもろい研究者になりませんか?勉強会、第3回を平成21年10月17日(土)に発生・再生科学総合研究センターにて開催した。今回の勉強会は、研究者自らイベントなどを企画する“企画力”のノウハウや実践を学ぶべく、天文分野で実際に様々なサイエンスコミュニケーションを行っているプロジェクト「天文学とプラネタリウム」通称“天プラ”の活動を紹介していただいた。講師には、天プラメンバーである、国立天文台研究員の高梨直紘氏、北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP)のスタッフである佐藤祐介氏、星の子館天文担当の塚田健氏をお招きした。天文学は科学コミュニケーションの中でも多くの実践例がある分野だけに、参加者からたくさんの質問が挙がり、活発な勉強会となった。また、高梨氏のご厚意により、参加者には星の輪廻が描かれたトイレットペーパー、Astronomical Toilet Paper略してATP(http://www.tenpla.net/atp/)がプレゼントされた。
当日の概要
第3回勉強会を開催
CDB広報国際化室おもろい研究者創出プロジェクト勉強会第2回を開催しました。
日時・場所
平成21年10月17日(土)
14:00~16:00
理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター
A棟7Fセミナー室
参加人数
12名
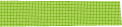
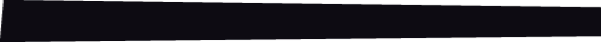

<講義概要>
天プラ代表高梨氏より、天プラの概要や基本姿勢、主な活動を紹介していただいた。
天文学とプラネタリウム「天プラ」について
天プラとは、プラネタリウムと協力した天文学の普及を目的とし、2003年に東京大学の大学院生だった高梨氏と平松氏が立ち上げたプロジェクトである。活動方針に、
①さまざまな背景を持った人間のコラボレーションに基づき
②既存の概念に囚われない自由な発想で
③それぞれの立場を活かした
④自分が楽しい活動をする
を掲げている。教育や啓蒙など“知らない人々に教える”といった姿勢とは異なる方向性で活動をしており、高梨氏曰く、「基本姿勢は趣味という範囲内で活動しています。」とのこと。初期は学生や科学館のスタッフが主なメンバーであったが、今では250名以上が登録し、研究員、学校教員、マスコミ関係者、デザイナー、主婦など、さまざまなバックグランドを持った方が参加されている。
天プラウェブサイト(http://www.tenpla.net/)
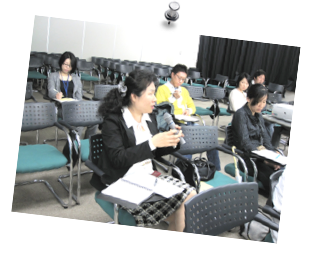
おもろい研究者になりませんか勉強会事務局スタッフ 松田一起
(発生・再生科学総合研究センター 生殖系列研究チーム)
<参加者へのアンケート結果>
Q1. 今回の勉強会の感想をお答えください。
・「実際に協働仲間を作る方法」の話が面白かったです。
・違う視点から物事を見ることができたように感じて非常によかったです。演者のポジティブな発想に元気をいただきました。
・活動を知ることができてよかった。
・講演者の話がおもしろく、楽しい講演には話し方が重要だと感じた。
・非常に考えさせられるところがあり、とても楽しかったです。
Q2. 今回の勉強会で得られたことをお答えください。
・科学者の世界観が分かって面白い。
・科学コミュニケーションとイベントの意義と企画について参考になった。
・科学コミュニケーションの場の創出。
・人とのコミュニケーション、結びつきが大事と知った。
・企画の段階的な発展と具体的な進め方。
・これからの研究者の在り方について考えるきっかけを得られました。
・知り合い・友人をたくさん作るのは重要。
Q3. 今後このような勉強会に参加したいですか。
Yes 10人No 0人
Q4. あなたは科学を広く伝えることの必要性を感じますか。
Yes 8人No 0人どちらとも言えない 1人無回答 1人
<Yesの理由>
・日本経済のため。
・飯のタネなのと、科学をsystem化するのに必要。
・科学技術の使い方を学ぶ、自分の人生観を構築するのに必要だと思う。
・政府がやるべきことをやっておられる。
・科学を伝えないとその必要性が認識されず、結局科学が廃れてしまうと思います。
・自分の研究費が税金から出るから。
<どちらとも言えない理由>
・漠然と「広く」伝えることの必要性はあまり感じない。しかし、ある特定の層には伝える必要性はある。
<どのような立場の人が伝えるべきだと思いますか。>
・研究者、子供を持つ親、身近な大人。
・これからは研究者が伝えていかないといけないと思いました。
天プラの活動
1.メンバー同士の交流活動
普段は主にメーリングリストを通じて意見交換をしているが、プラネタリウム見学会や交流会(という名の飲み会)を各所で開き、親睦を深めている。お酒の席で冗談を交えながら議論することで、あたらしいアイデアが生まれることもあるそうだ。先述のATP(トイレットペーパー)もそのひとつである。
-
2.天文学の普及活動
年に30回程度、講演やイベントを開催しており、著名な研究者や大学教授ではなく、主に大学院生が活動している。「学生だから伝えられる天文学があります。尻込みしないで、どんどん参加した方がいい。」と高梨氏。若い人の方が、子どもにとっては年齢が近く、大人にとっては自分の息子や娘と同世代になるので親近感を抱きやすい。講演会の反応は、若手研究者の熱意が良く伝わってきたという声が多いそうだ。
また、様々な団体とコラボレーションすることもある。たとえば、飛行場にある喫茶店。離発着のない夜間を利用して、滑走路で星を眺める天体観望会とサイエンスカフェを開催した。飛行場の宣伝にもなり、双方にメリットがある取り組みだ。
天文グッズも作成している(ウェブサイトで公開)。
・ トイレットペーパー:科学館やオンライショップで販売。
・ 宇宙図:一家に一枚シリーズ
・ あすとろかるた:表はかわいいイラストだが、裏にマニアックな解説。
・ タイピングゲーム:うまくプレイすると、その言葉の解説を読むことができる。
3.普及活動の普及活動
科学コミュニケーションの普及活動のことである。学会や学校、科学館で開催し、この勉強会もこれにあたる。また、新聞やテレビ、雑誌等のマスメディアにも露出している。

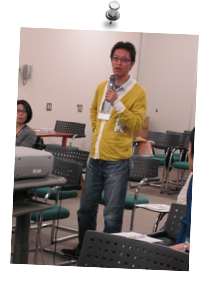
「天プラは“一期一会”を意識した活動を行っています。」今まで天文学に興味を持たなかった人たちに興味を持ってもらうようにするには、相手の興味を“一瞬”で引き出すことが重要である。もし、その人がつまらないと感じたら、そのままずっと興味を持ってくれないかもしれない。
高梨氏の活動紹介に続いて、佐藤氏より、研究者が天プラのようなイベントを開催する際の「企画力」について講義していただいた。
企画に必要なもの
「おもろい研究者とかけて、冒険物語の主人公と解く、その心は?」佐藤氏はこう話を切り出した。何かを企画して実行するためには、資金・人材・物品を用意しなくてはならない。しかし、真に必要なものは“新しいアイデア”と“コミュニティ(社会的関係性)”だという。
・新しいアイデアは既存のアイデアのマッシュアップである(「アイデアのつくりかた」より)。
・アイデアは人と人をつなげることによって生まれる(「コミュニティ・オブ・プラクティス」より)。
「アイデアはコミュニティによって生まれます。そして、コミュニティの発展は既に存在する社会的ネットワークから始まりまるのです。」
先のなぞかけの答えは“良い仲間がたくさんいる”こと。ある志を持って行動する人には、同じ志を持った仲間が集まる。1人では妄想だけで終わることもあるが、2人いれば議論できる。3人ならそれを実行に移せるが、一回で力尽きる。5人いれば負担は分散し、アイデアが生まれ、また新たな人脈を作ることができるだろう。
<質疑応答>
Q.科学コミュニケーションを仕事としてする場合とボランティア(趣味)としてする場合、どうやってバランスをとっているのですか?
A.あまり区別なくやっています。周りに役立つことなら枠を変える。関係者に働きかけます。自分の楽しめることをいかに仕事に織り込むかですね。
Q.資金源は何ですか?
A.JSTなど個人で貰える助成金があります。あとはグッズの売り上げです。身銭を切ったこともあります。
Q.イベントに参加した人に「また来たい!」と思わせるにはどうしたらいいですか?
A.ターゲットを絞って、小規模でやる方がそう思われやすいです。
Q.サイエンスカフェを運営しているのですが、興味のある人しか来てくれません。人集めはどうすればいいですか?
A.科学系の人にだけ情報を流すのではなく、NPOなど特定のネットワークを形成しているところに流す。主婦には主婦のネットワークがあります。ターゲットを絞るのもいいです。また、自分たちから人の集まる場所へ出向いた方がいいです。
